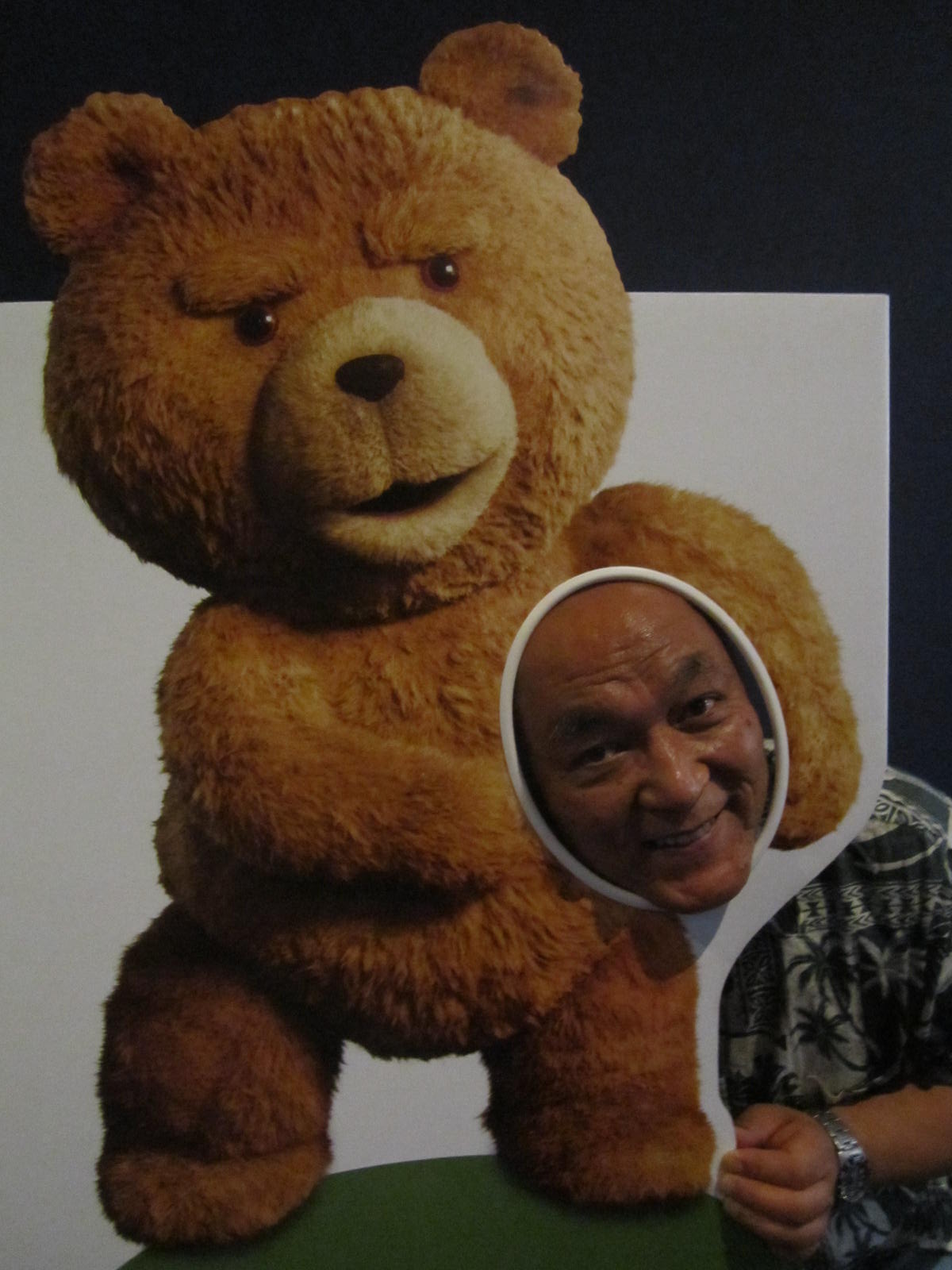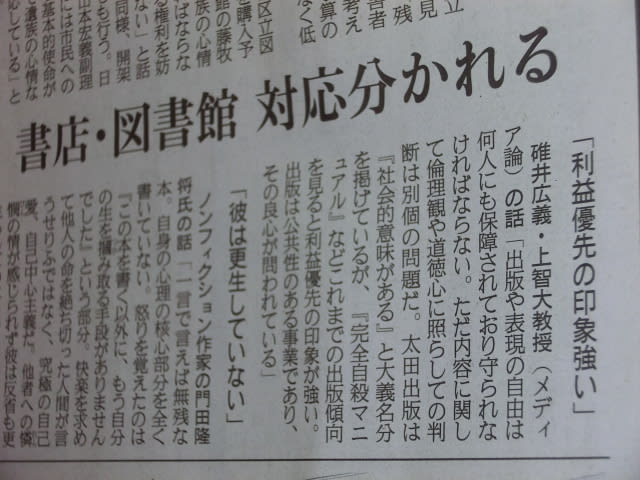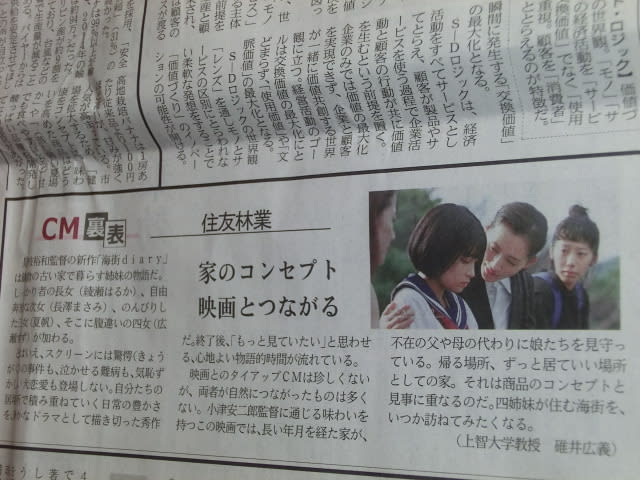「ヨルタモリ」でバラエティ初レギュラーを務める宮沢りえが好評だ。下ネタも、愚痴も、軽妙に受け答える和服姿の四十路色香は、日曜夜の憂鬱な気持ちを癒やしてくれる。紆余曲折の人生から、開眼した新たな魅力。女優の枠にはおさまらない脱皮した「スター」の素顔が今、実名証言で明かされる。
昨年10月19日に放送が始まった「ヨルタモリ」(フジテレビ系)で女性MCを務める宮沢りえ(42)。女優一筋の宮沢がバラエティ初レギュラーに踏み切った理由をフジテレビ関係者が明かす。
「以前から、タモリさんと宮沢さんは都内の同じバーに行っています。遭遇すると、タモリさんが『今からじっと2分間、見つめていいですか?』と冗談を言うほどの仲です。企画段階で、タモリさんがラブコールを送り、出演が決まったんです」
日曜夜11時台という深夜帯の放送ながら2桁台の視聴率をマークする回があり、好調を維持している「ヨルタモリ」。宮沢は、東京下町の湯島のバーのママ役という設定だが、毎回着物姿で四十路の色香を振りまいている。
メディア論を専門にする上智大学の碓井広義教授がその魅力を語る。
「まだ10代の時にCMの撮影現場で出会ったことがあります。宮沢さんがスタジオに入ると現場が急にパッと明るく華やいだのを覚えています。『ヨルタモリ』を見ていても、それを感じますよね。しかも、その華やかさがまったくもってくすんでいない。それどころか、ますます大人の魅力を増し、チャーミングになっている。稀有な女優さんですよね」
番組でタモリは岩手県在住のジャズ喫茶のマスター「ヨシワラさん」に扮する。ややなまった「ヨシワラさん」と「りえママ」との軽妙洒脱なやりとり。この新たな一面が人気となり再ブレイクしているのだ。
「いい意味で女優然としていない。42歳の素の自分をさらけ出していますよね。肩肘張らない自然体の姿は最大のチャーミングポイントです」(碓井氏)
3月1日の放送回では、「ヨシワラさん」が、
「何で女性って下ネタ言わないのかね」
と、つぶやくと宮沢は、
「いや。言いますよ。私、下ネタ好き。だって罪がないじゃない。誰も傷つけないし」
と「下ネタ好き」であることを告白している。
大物ころがしも堂に入ったものだ。
4月26日の回では、とんねるずの石橋貴明(53)がゲスト出演。93年、当時関脇だった貴花田との婚約発表前日に宮沢に電話したが、つながらなかったことを悔やんだ。そして婚約破棄の一件をネタにしたのだ。
「こっちの“貴”にしておけばよかったのに」
宮沢は過去の傷を笑顔で返すのだった。
「電話がもっと早かったら、私も婚約していなかったかも」
また、5月31日には松本幸四郎(72)がゲストで登場。珍しいバラエティ出演の理由をこう明かした。
「トークは苦手だけど、りえちゃんの頼みなら」
「世界の北野」ビートたけし(68)も、宮沢にラブコールを送る一人だ。
今年2月22日に行われた「第24回東京スポーツ映画大賞」の授賞式で、審査委員長を務めたたけしは、
「アイドル時代があって、いろいろあって脱皮していった。普通はアイドルの服を着たまま大きくなっていくが、どんどん脱いで脱皮した」
と宮沢を大絶賛した。
「ヨルタモリ」にはこれまで井上陽水、黒柳徹子など超大物が出演している。
「若手から大物まで、幅広い世代に愛されている。先日も沢尻エリカさんが出演したのですが、終始上機嫌でした。宮沢さん効果で『ヨルタモリ』に出たいと、みずから出演を売り込んでくるタレントさんもいます。明石家さんまさんもその一人」(フジテレビ関係者)
タモリとはカメラが回っていないところでも料理の話で盛り上がり、公私に渡る関係は良好だという。
(週刊アサヒ芸能 2015年 6月18日号)