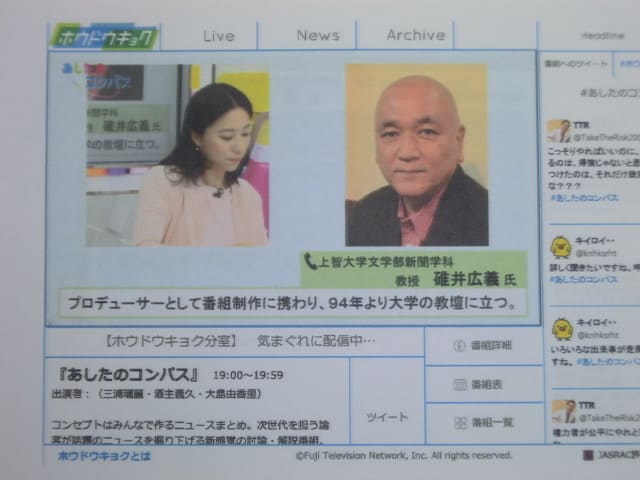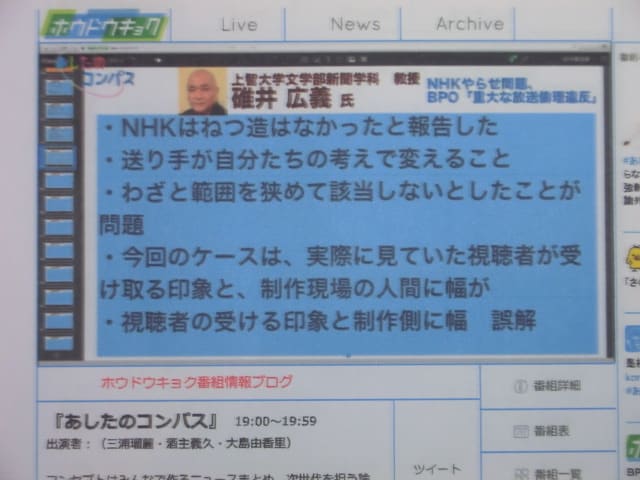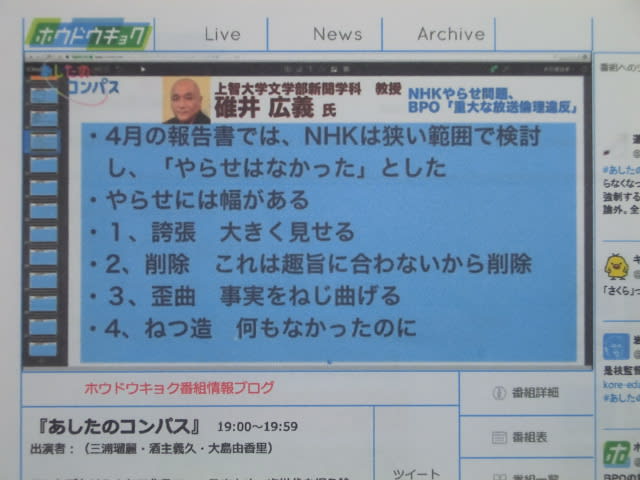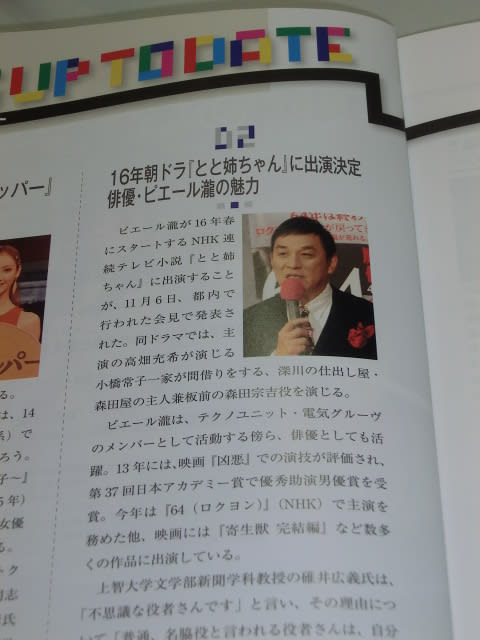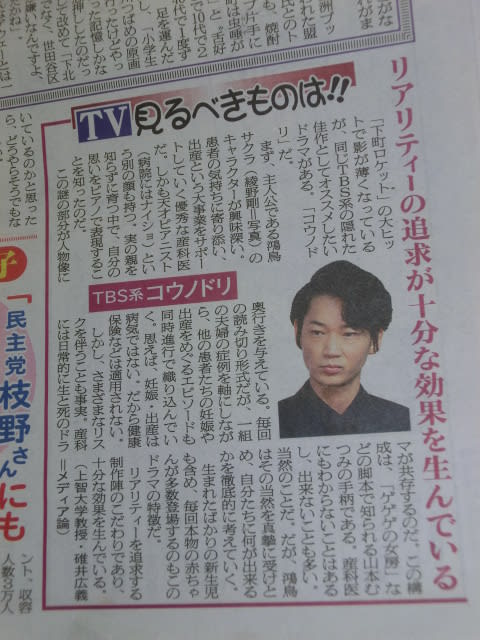Image may be NSFW.
週刊現代に掲載された、「下町ロケット」の特集記事が、現代ビジネスにアップされました。
この記事の中でコメントしています。
『下町ロケット』の快進撃が止まらない!
夢を諦めない男たちにグッとくるのはなぜか
阿部寛ら出演者・専門家が語る
あの池井戸潤の原作で、阿部寛が主演。期待は大きかったけれど、それを上回る面白さだ。社会人なら誰もが挫折を味わう。それでも、諦められない夢がある。「大人のドラマ」から目が離せない。
■阿部寛が熱く語る
「佃のような中小企業の経営者は、これまでにまったく演じたことがないタイプですね。ただ、僕は父も兄もエンジニアでした。僕自身、大学は電気工学科だったのですが、子供の頃は、漠然とした宇宙への憧れがあった。だから佃には共感するところもあります」
TBS系ドラマ『下町ロケット』で主人公・佃航平を演じる阿部寛はそう語る。
「僕の役は、元ロケットエンジンの開発者で、現在は家業を継ぎ、下町の中小企業を経営する男。経営上の苦難や社員との軋轢に葛藤しながら、若い頃の宇宙への夢を捨てられない主人公です。
経営者なら、もちろん現実も見なければいけません。ですが、僕個人としては、夢は捨てたら終わりだと思っています。夢も、そして技術も、失ったものはもう帰ってこないのですから」
『下町ロケット』の快進撃が止まらない。10月18日放送の初回が16.1%の高視聴率で、第2話では17.8%を叩きだした。'13年夏放送の『半沢直樹』の人気を再現しそうな勢いだ。
阿部をはじめとした人気俳優の起用。原作はヒットメーカー・池井戸潤の直木賞受賞作。そして、『半沢直樹』と同じ制作陣。放送前からヒットの予感をさせたが、『下町ロケット』が見る者に感動を与えているのは、阿部がいう「夢を諦めない人々」の人間ドラマを、説得力を持って描いているからだ。
それを象徴するのが、11月1日に放送された3話の名シーンだ。佃航平は力強くこう熱弁した。
「カネの問題じゃない。これはエンジンメーカーとしての、夢とプライドの問題なんだ!」
純国産でのロケット開発に邁進する、日本を代表する帝国重工。莫大な費用と長い年月をかけた研究の末、ついにロケットの鍵となる「水素エンジンのバルブシステム」の開発に成功する。
しかし、そのバルブシステムの開発には、実は佃が先に成功し、特許も取得していた。「特許を買い上げたい」と持ちかける帝国重工の宇宙航空部部長・財前道生(吉川晃司)。提案にどう応えるか、佃社内で議論が紛糾する。
特許を可能な限り高く売却しようという声、特許使用契約を結んで、技術は保持しつつ長期的な収益を確保するべきという声。様々な意見のなか、佃航平が決めたのが、
「バルブシステムの部品を佃製作所で作り、帝国重工と受注契約する」
という方針だった。夢物語のような提案に、社員から異論が噴出。それを制するように放ったのが、先の台詞だ。
撮影現場にも男たちの熱気が満ちている。佃製作所営業第一部部長・津野薫役の中本賢が語る。
「現場では、阿部さんが作品の中の佃航平以上と言えるくらい大きな役割を担って、出演者をリードしてくれています。男ばかりの現場で、いつもテンション高く、ラグビーでスクラムを組むような連帯感があるんです。ドラマの雰囲気そのままで撮影が進んでいます。
その相乗効果もあって、感情を高ぶらせるようなシーンでは、たとえそれが佃航平の台詞だとわかっていても、阿部さんの言葉のように聞こえてしまう。心に沁みてくるんですよね。撮影中、みんな本気で泣いています(笑)。それは役者としてとても嬉しいことです」
■「出向銀行マン」の意地
役者たちの熱演に加え、物語にリアリティを与えているのが、『半沢直樹』でも見られた撮影手法。セットに頼らず、既存の会社や工場などで撮影が行われている。佃製作所でのシーンも、古くからの町工場が立ち並ぶ蒲田の、実際の社屋で行うという徹底ぶりだ。
その社屋の一室で、再び阿部が語る。
「ここも、戦前からある建造物と聞いて、『そんなに歴史を重ねてきたのか』とびっくりしました。戦争にも、多摩川の水害にも負けず、ずっとこの地に根付いてきた。そんな町工場の頑張りを意気に感じながら、佃航平を演じています。
ここには、僕より年上の機械類が並んでいる。これを見ていたら、工場を人手に渡す経営者の悲しい気持ちがわかってきてね。これまで懸命に油を注いで、整備してきた機械を人手に絶対渡したくないという思いがこみあげてきました。
ドラマのなかでも難題にぶつかった佃が『ちくしょう』と悔しがるシーンがたくさんありますが、そんな実感をこめています」
佃航平の人間性が伝わってきたのが、第2話のクライマックス、ナカシマ工業との裁判で、自ら証人尋問に立つシーンだ。
いわれのない特許権侵害訴訟を起こされた佃が、ナカシマ工業の顧問弁護士・中川京一(池畑慎之介)の技術者をバカにしたような嫌らしい質問に、こう反論する。
「たとえこの裁判に負けたとしても、ナカシマに特許を奪われたとしても、屁でもありません。培ってきた技術力だけは決して奪えない。正義は我にありだ!」
その実直な言葉が裁判長の心を動かし、佃の実質勝訴の和解という決着を生む。
上智大学新聞学科の碓井広義教授(メディア論)もそのシーンに「グッときた」という。
「普段スポットの当たらない技術者たち、モノを作る人たちの思いを代弁してくれた名台詞でした。俺たちの言いたいことを言ってくれた。そう快哉を叫んだ人も多いんじゃないでしょうか。
演出の福澤克雄さんの手腕だと思うのですが、それまでの訴訟の攻防がサスペンス色強く描かれているため、証人尋問のシーンが盛り上がり、綺麗事に聞こえがちな台詞もスッと心に入ってくる。阿部さんの目を真っ赤にした演技も迫真でした」
もちろん、理想だけでビジネスは成り立たないのも事実。そんな現実をしっかり描いているのも、このドラマの魅力だ。
なかでも、佃製作所の資金繰りに奔走する経理部長・殿村直弘(立川談春)の存在感が際立つ。メインバンク・白水銀行から出向中という、いわば「よそ者」の立場。法政大学社会学部教授で元テレビディレクターの水島宏明氏はこう言う。
「私が共感するのは殿村です。50代になると、大学の同期で銀行員になった連中にも、殿村のように出向になった人が多い。すると、『結局はウチの人間じゃない』とイジメられたりして、鬱になってしまう人もいるんですよ。
他の社員の陰口をバックに、殿村が一人居酒屋で酒を飲むシーンがありましたが、サラリーマンの切なさを立川談春さんがとてもうまく表現していました。だからこそ、経営の危機に瀕しながら『この会社が好きなんです』と殿村が叫ぶシーンや、出向元の白水銀行と袂を分かつ決断などが、心に響くんです」
■普通の人間が頑張る物語
佃vs.帝国という中小企業対大企業の構図だけではなく、佃社内での意見の対立も丁寧に描かれる。組織の論理が先にあって個人がいるのではなく、個人の思いの集積が、組織を作る。そんなテーマが内包されている。
経理の殿村や営業の津野、技術開発部長の山崎光彦(安田顕)、熱血漢の営業第二部部長・唐木田篤(谷田歩)らが、会社の方針をめぐって激しく意見をぶつけあうシーンはもはやお馴染みだ。
「満員電車で通勤しているような、普通の人間を思い浮かべて」津野を演じているという、中本賢が語る。
「経営は一筋縄ではいかない話です。ただ、津野にとって特許だカネだという話は本筋ではなくて、まず『佃航平についていこう』という思いがある。
先代の頃から勤めている津野としては、希望に燃える若旦那に引っ張られて『この社長の思いを実現してあげたい』と、佃の人としての魅力に惹かれている。その純粋な思いがモチベーションなんです」
第3話では、夢を追う佃やそれを支える山崎と、目の前の利益を求める若手社員の間にミゾが生まれる。ドラマは前半の山場、帝国重工との決着に向かっているが、その社員同士の対立が、物語の行方に大きく関わってくる。
阿部寛が語る。
「実際に中小企業の経営者たちに話を聞いても、在庫を抱えて資金繰りに苦しんだり、人間関係で悩んだり、日々問題が起こっている。従業員から社長まで、時に妥協しながらも、誇りを失わずに生きているんだなと感じます。そんな人たちを応援する作品にしたい」
これからも、日曜21時を楽しみにしよう。
(週刊現代 2015年11月14日号より)